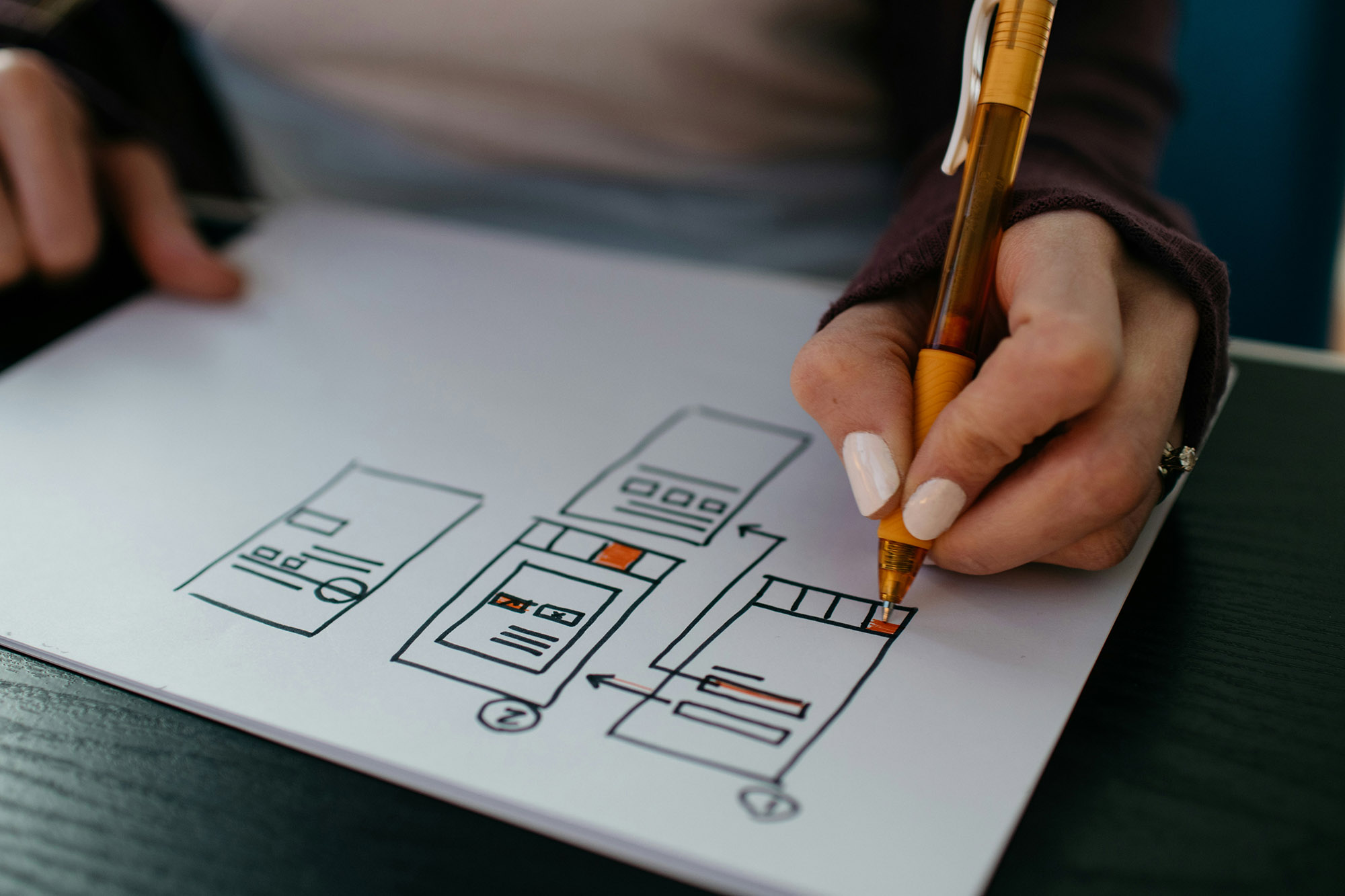- HOME
- DIGITAL LAB
- ChatGPTを味方につける - AI時代のコンテンツ戦略
ネットの悪評で売上が止まる前に。企業を守るための“戦略的風評対策”

どれだけ誠実にビジネスをしていても、ある日突然、ネット上に書き込まれたたった1つの悪評で信用が崩れる──。
これは、もはや珍しい話ではありません。
現代において、WEB上の評価=会社の印象と言っても過言ではない時代です。
一度広まったネガティブな印象は、放っておいても自然に消えることはほとんどありません。
むしろ放置すればするほど、検索上位に表示され、信頼の低下、問い合わせ数の減少、求人応募率の低下など、目に見える形で“損失”が現れ始めます。
ネットの悪評は「火」ではなく「煙」から対処する
風評被害というと、「拡散されたあと」の火消しばかりに意識が向きがちですが、
本当に大事なのは“火種の芽を摘む”戦略です。
たとえば、以下のような兆候が出ていたら要注意です:
- 検索ワードのサジェストに「やばい」「最悪」「詐欺」などが出てきた
- Googleレビューに根拠のない★1レビューがついた
- 掲示板や匿名サイトで社名が出ている
- SNSで社員の匿名アカウントが何かを発信している
これらは、表面上は静かでも「煙」が立っている状態です。
この段階で手を打つかどうかが、その後の被害規模を大きく左右します。
“戦略的対策”と“感情的反応”の違い
多くの企業がやってしまう間違いは、「風評被害に感情で反応してしまう」ことです。
例えば、掲示板に反論を書き込む、レビューに怒りの返信をする、社員に強い言葉で注意する──こうした行動は一見対処しているように見えて、火に油を注ぐ結果になりやすいのです。
倉持竜太が提案するのは、冷静で戦略的なアプローチです。
それは、以下の3つの軸で構成されています:
- 検索対策(リスクワードの押し下げ)
ネガティブなワードやページを“見えにくくする”ためのSEO施策。ポジティブな情報で検索結果を上書きし、風評ページを事実上無力化させます。 - プラットフォーム対応(レビュー・SNS等)
規約に違反する投稿への削除申請や、レビュー戦略による評価バランスの最適化。同時に、ポジティブレビューを増やす自然な仕組みを導入します。 - ブランドの“防御力”を高める情報設計
オウンドメディアや採用ページ、代表挨拶、理念コンテンツなど、「信頼を育てる発信」によって、ネガティブな印象を打ち消す土台を作ります。
風評被害対策は“企業の信用資産”を守ること
風評被害は、目に見えにくい形で「信用」という資産を蝕んでいきます。
それは広告でも買えない、唯一無二の価値。
もし今、
「社名+評判」で検索されて嫌なページが出てきたら、
「会社名で調べると掲示板が上に来てしまっている」
そんな状況があるなら、それは「すでに始まっているリスク」です。
対策は早ければ早いほど効果的です。
そして、一度“信用”を失うと、回復には倍以上のコストと時間がかかる。
だからこそ、感情的に反応するのではなく、戦略的に守る必要があります。
倉持竜太が提供するのは、「見えないリスクを数字で可視化し、仕組みで抑える」WEB戦略です。
最後に:守ることもまた、攻めである
風評被害への対策は、防御であると同時に、“信頼で攻める”施策でもあります。
検索画面がきれいに整っていれば、それは無言のブランディングです。ユーザーの不安を解消し、安心感を提供する構造そのものが、選ばれる理由になるのです。
“攻めるために守る”という視点を、今こそ持ちましょう。
あなたの会社の未来を、ネガティブな噂ひとつに揺るがせないために。